症徴とは、症状(自覚症状)と徴候(他覚所見)を合わせたものです。
患者ひとりひとりに合った栄養学的なアプローチも治療の一環となります。
発熱
生体内に何らかの異常が起きると、整体防御反応のために体温が上昇する。
感染症、膠原病、悪性リンパ腫などの場合には発熱する。
発熱時らエネルギー代謝が更新するので、エネルギー補給が必須となる。
呼吸困難
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の場合は糖質の多い食事を避け、高脂肪食にすると緩和する。
水分摂取量が少ないと痰が出にくくなるため、十分に補給するようにする。
肥満とるいそう
体脂肪が過剰に蓄積した状態を肥満といい、
非常に少ない場合がるいそう(やせ、低体重)という。
遺伝的要素もあるが、食事や運動による生活習慣の改善が必須。
発疹
皮膚にみられる肉眼的な変化。
食物や薬などが主な原因で、食事性中毒疹では蕁麻疹が代表的。
食事性の場合は原因食品を特定し、食事から除去する。
貧血
血中のヘモグロビン濃度または赤血球数が正常値以下になった状態。
チューブによる経管栄養法で鉄や亜鉛が欠乏するケースも多い。
欠乏している栄養素の補充が重要。
浮腫と脱水
浮腫とは細胞外液が過剰に増えた状態。
脱水とは細胞外液が減少した状態。
原因疾患が様々で、それに応じた栄養管理が必要になる。
脱水の場合は、水分量と塩分量の管理が極めて重要。
腹部膨隆
鼓腸(腸管内に大量のガスがたまる)と、腹水(腸管外の腹腔内に大量の液体がたまる)がある。
前者はガスを発生しやすい食品を避け、
後者は疾患の治療が重要(安静、減塩食を含む)。
黄疸
皮膚および眼球結膜などの粘膜部が黄色くなる。
血清ビリルビン濃度が2.0mg/dl以上の場合は顕性黄疸と呼ばれる。
肝炎、胆石、膵がんなどが原因。
疾患によっては脂肪の摂取量を減らす。
食欲不振
長期的な食欲不振は栄養状態を悪化させる。
食欲は脳によって調整されているが、精神状態も大きく影響する。
楽しく、リラックスできる食環境づくりも重要。
下痢と便秘
下痢や便秘は原因やタイプも様々。
下痢の場合は脱水症状が現れるケースがあるので、十分に水分を補給する。
便秘は食事や運動などの生活改善の試みが必要。
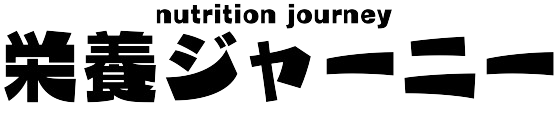
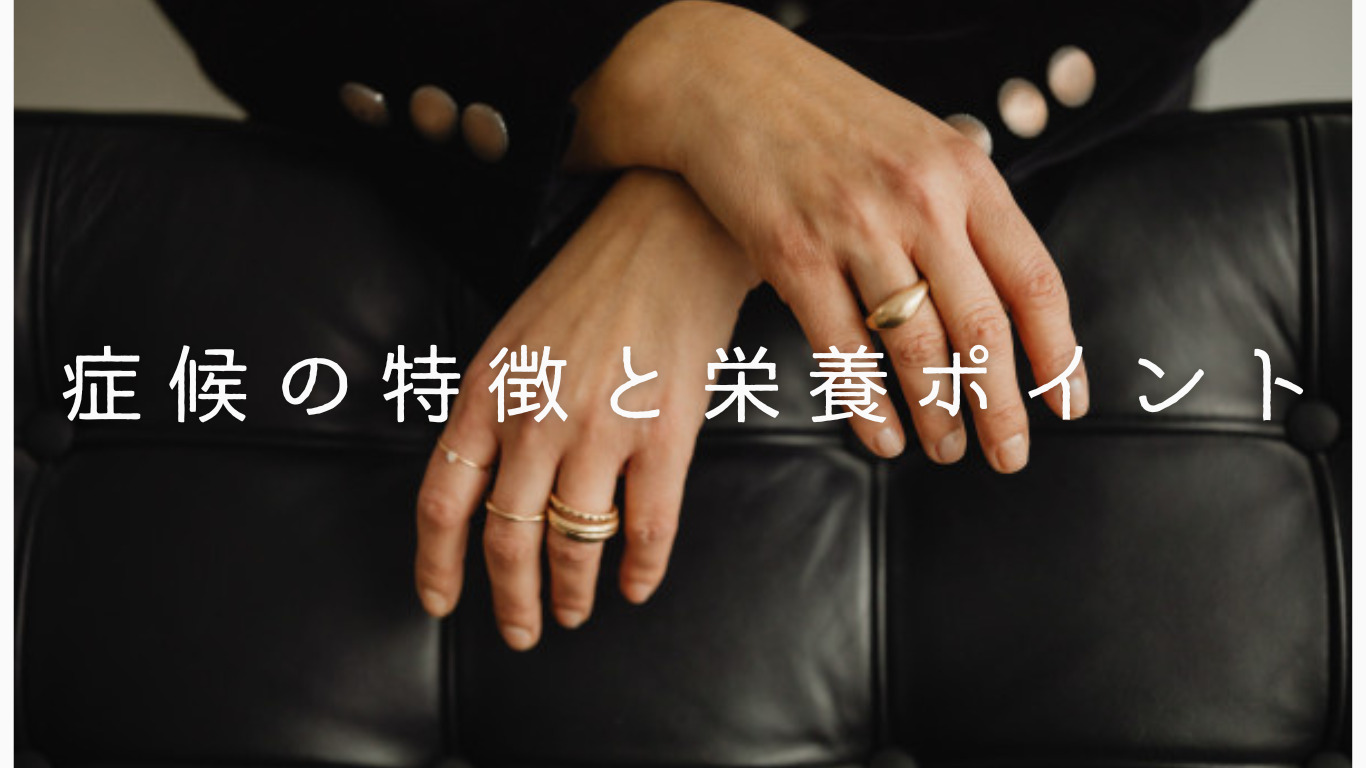


コメント