救急病棟で早期栄養介入管理加算の運用を開始してから、半年が経とうとしています。
ほんと時が経つのはあっという間ですね。
いつの間にか秋も終わりそうで、もうすぐ冬ですよみなさん…。
さてさて、今回は早期栄養介入管理加算のアウトカムについて考えていきます。
以前も記事にしましたが、結構な額の加算を毎日毎日取っているわけなので、その効果を示していかなくてはならないわけです。
でもどうやってそれを評価すればいいのか、最近はそんなこをとを考えています。
救急病棟に在室している期間は、もちろん患者の状態によって様々です。
でも体感としては数日の間には一般の病棟に転棟しているのではないかと思っています。
(きっちり調べればいいのですが割愛します)
それでその短い数日間のうちに、管理栄養士が早期から介入してなにか効果があったのかを知りたいわけです。
栄養状態と一言でいっても様々で、
採血データ…とくにアルブミンは炎症反応に左右されますし、半減期も長いので微妙…
体重は補液ガンガン投与すればそれだけで増えるので単純に評価はできない。
となると、必要栄養量の充足率あたりになるのだろうか。
日本版重症患者の栄養療法ガイドライン によれば、予後を考えたときにエネルギー量は1週間で必要量の約6−7割、蛋白質は1.2g/kgが目安となっています。
救急病棟に入室(介入開始)してから、退室するまでどの程度充足できているのかを見てみるのはありかもしれない。
ただし、その数値をアナログに管理するのはナンセンスなのでどうにか機械的に集計できるシステムを考えてみよう…!
みなさんの施設では早期栄養介入管理加算のアウトカムはどのように行っていますか?
いい案があれば教えてほしいです♪

[徹底解説]早期栄養介入管理加算の見直し
【I-3医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑫】 第1 基本的な考え方患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点か...

[考える]急性期病院における早期栄養介入管理加算の実際
診療報酬の改訂で今年度から早期栄養介入管理加算がICU以外※でも取得できるようになったので、当院でも運用を開始しました。...
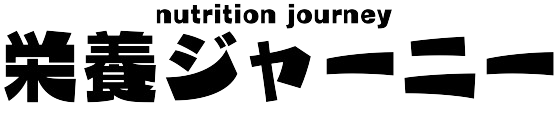
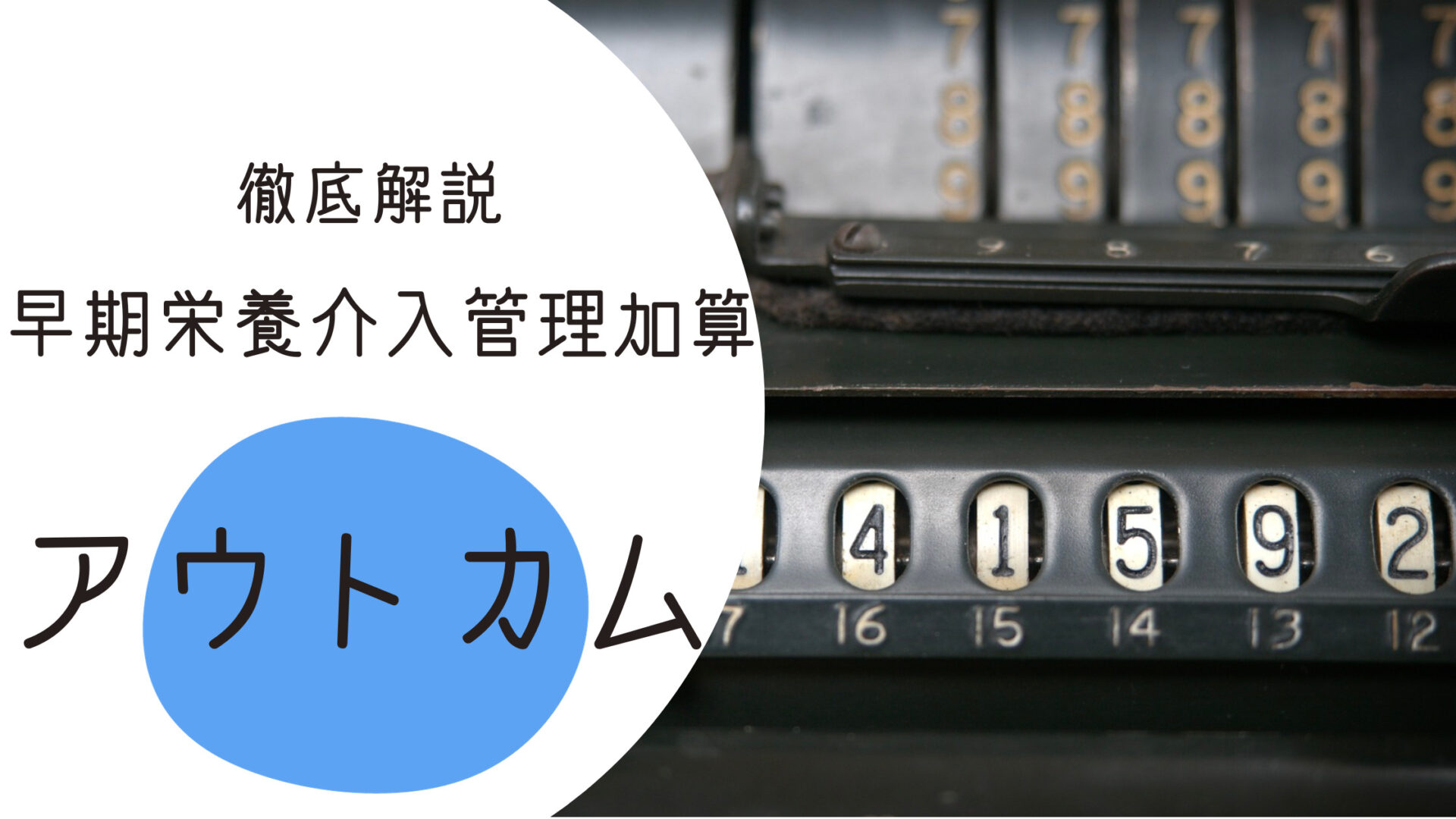


コメント